
新入荷
再入荷
〈図解〉武将・剣豪と日本刀 新装版 日本武具研究会 最低限知っておきたい刀剣の基本名刀とその持ち主にまつわるエピソードを解説。
 タイムセール
タイムセール
終了まで
00
00
00
999円以上お買上げで送料無料(※)
999円以上お買上げで代引き手数料無料
999円以上お買上げで代引き手数料無料
通販と店舗では販売価格や税表示が異なる場合がございます。また店頭ではすでに品切れの場合もございます。予めご了承ください。
商品詳細情報
| 管理番号 |
新品 :40769169010
中古 :40769169010-1 |
メーカー | f6216 | 発売日 | 2025-04-21 21:18 | 定価 | 1918円 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ | |||||||||






















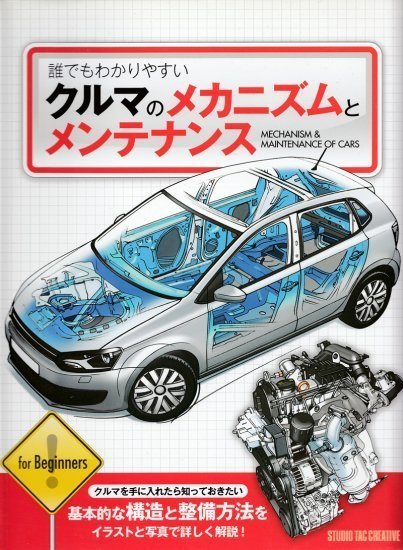















[図解]武将・剣豪と日本刀 新装版
最低限知っておきたい刀剣の基本
名刀とその持ち主にまつわるエピソードを解説。
目次
【第一章】日本刀の歴史
・解説
・縄文から奈良
・平安から鎌倉
・南北朝から室町
・安土桃山から江戸
・江戸中期から幕末
・コラム「日本刀の製法」
【第二章】図解・日本刀
・解説
・刀剣の形状分類
・刀剣各部の名称と種類
・刀剣の特徴と見所
・刀を彩る「拵」1…刀装
・刀を彩る「拵」2…鐔
・刀を彩る「拵」3…小柄・竿
・刀を彩る「拵」4…柄
・コラム「土壇ってなに」
【第三章】武将・剣豪たちと名刀
・解説
・平家の刀と小鳥丸
・坂上田村麻呂と黒漆大刀
・藤原秀郷と毛抜太刀
・源頼光と童子切安綱
・源氏重代の剣と膝丸
・北条時政と鬼丸国綱
・楠木正成と小龍景光
・源頼政と獅子王
・渡辺綱・新田義貞と鬼切国綱
・梶原景時と狐ヶ崎為次
・佐々木道誉と一文字
・足利義輝と大般若長光
・城昌茂と津軽正宗
・細川幽斎と古今伝授行平
・細川忠興と歌仙兼定
・毛利元就と福岡一文字
・池田輝政と大包平
・石田三成と石田切込正宗
・丹羽長秀とニッカリ青江
・奥平信昌と一文字
・真田幸村と千子村正
・松平家と明石國行
・前田家と大典太光世
・伊達政宗と名刀
・直江兼続と三条宗近
・武田信玄と一文字の太刀
・上杉謙信が愛した刀
・織田信長とへし切長谷部、他
・豊臣秀吉と一期一振
・徳川家康とソハヤノツルキ
・柳生連也斎の刀
・土方歳三と和泉守兼定
・近藤勇と虎徹
・コラム「幻の刀、試製拳銃付軍刀」
【第四章】名匠伝
・解説
・天国
・宗近
・政宗
・孫六兼元
・後藤羽院
・刀剣にまつわる言葉
・博物館ガイド
・参考文献
・索引
・プロフィール
レビューより
日本刀の歴史や種類、それを使った剣豪たちが分類、図説されてわかり易く解説されていて理解しやすい武将、剣豪と日本刀の解説書であった。剣豪や日本刀のことを知りたい人には事典として使える本である。
本の構成は、巻頭は、写真カタログ 一章:歴史 二章:形状図解 三章:名刀と所持武将の解説 四章:作匠者解説 の構成 主は第三章で、35項の大半を構成している。
自分の漢字読み能力も低いと思うが、専門部位の漢字がまず読めない。拵(こしらえ)鋒(きっさき)鎬(しのぎ)茎(なかご)鑢(やすり)鍔(つば)他 普段現代の生活では、使用頻度の低い漢字が、容赦なく出てくるので、最初の頃は、前に戻りながら、茎ってどの部分のことだっけ?などと確認しながら読み進む必要があります。読み進むうちに、名刀にまつわるエピソードとともに、日本刀の知識も身についていくようです。
時代劇などで、太刀と打刀の違いなど、意識したことなかったですが、本書でそれが理解できたり、他人の名刀を拝刀する際、どこを着目して、検分しているのか?がわかります。銘刀は、時代を重ねて技術革新がおき、後年なら後年の作ほうが良いような気もしますが、それは間違いで、大抵のものが、室町時代 鎌倉時代の作であることにも驚愕します。砂鉄と炭火から作るのですからね。
巻末には、刀から発祥の現代でも使っている言葉集「切羽つまる」「抜き打ち」「鞘当」などから、武士文化のなごりが大きいことや、全国 日本刀が見られる博物館マップなど、日本刀や時代劇ファンのどちらかというと初心者は、購入して損はないと思います。